◆はじめに
AI技術の進展に伴い、AI関連の特許をめぐる訴訟も国内外で増加しています。これらの訴訟事例からは、単なる特許取得だけでなく、特許の活用や管理、契約・ライセンス戦略まで含めた知財戦略全体の重要性が浮き彫りになります。
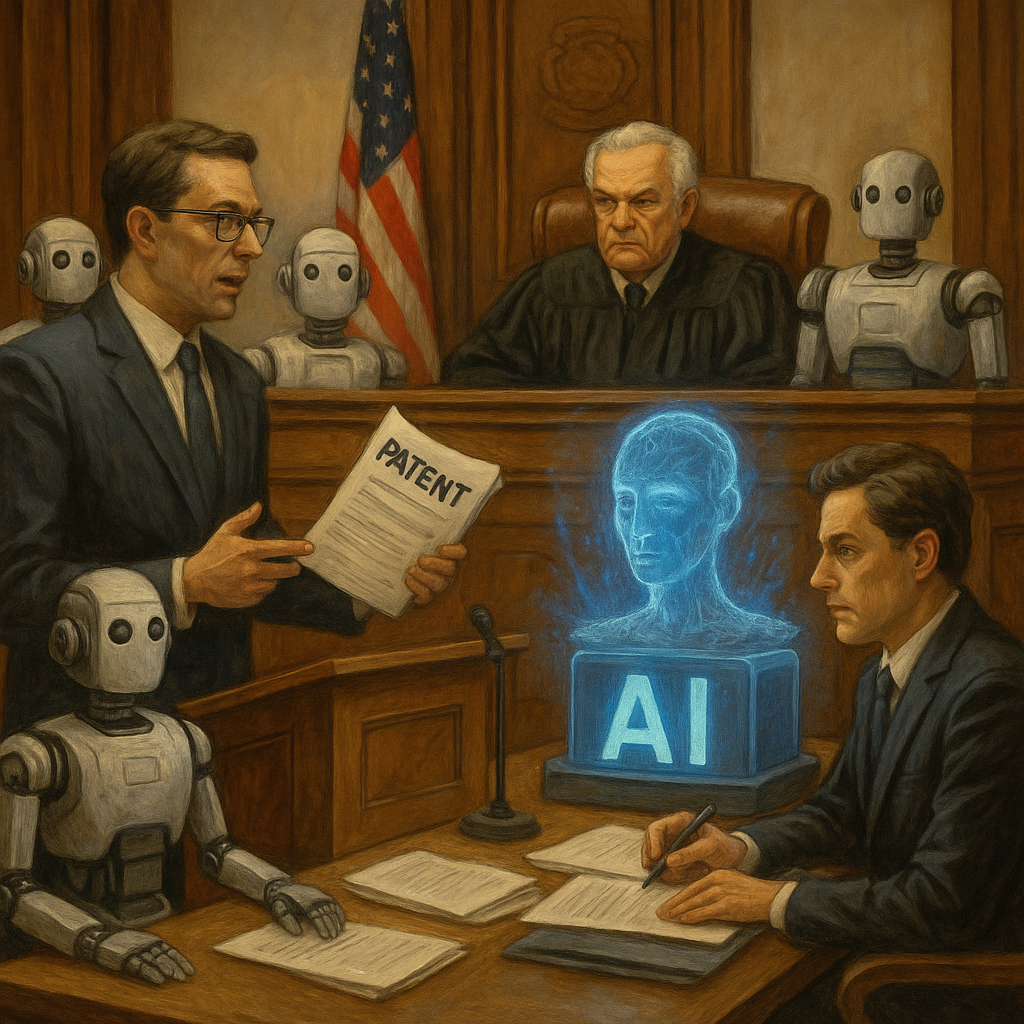
1. AI関連訴訟の傾向
近年のAI関連特許訴訟には、以下のような特徴が見られます:
・アルゴリズムや推論処理の構成が争点となるケース
・データ処理・機械学習モデルの実装方法に関する侵害主張
・スタートアップと大企業間での係争が増加傾向
・学習済みモデルやクラウドAI APIの利用に関するライセンス条項違反が訴訟に発展するケース
2. 海外における注目事例
・米国では、大手IT企業が保有するAI関連特許を巡って、複数の訴訟が提起されています。特に自然言語処理、音声認識、画像分類といった応用分野において、モデル構成の細部が特許請求項に該当するか否かが争点となっています。
・欧州でも、AIによる自動運転技術を巡る訴訟が注目されています。アルゴリズムのブラックボックス性が高いため、証拠収集や侵害立証に困難が生じる例もあります。
・その他、英国でもAIに関する以下のような訴訟が提起され、様々な論点について争われています。
① Getty Images 対 Stability AI(英国)
Getty Images が、Stability AI の画像生成システム(例えば Stable Diffusion)に対し、自社のストック画像を学習データとして利用されたとして訴訟を提起しました。
結果として、ロンドンの裁判所で Getty Images が「大部分で敗訴」に近い判断を受けたと報じられています。
学び:生成AI(特に画像生成モデル)を巡る学習データの利用や著作物の取り扱い、モデル構築/運用時の法的リスクが顕在化している点。AI特許だけでなく、データ・著作権・利用契約が絡むため、出願・実施・ライセンスの観点で包括的な対応が必要です。
② Emotional Perception AI Ltd 対 UK IPO(英国)
同社が「感情応答(emotion‑based)を利用したメディア推薦用ニューラルネットワーク」に関する特許(あるいは出願)をめぐり、英国の特許庁長官に対する異議申立て・審判を行った案件が報じられています。
本件は、AIモデル(ニューラルネット)自体が特許適格性を有するか、またその構成・機能が十分に明示されているかが争点となっています。
学び:AI関連発明を出願する際には、単に「ニューラルネットを用いる」という記載だけでは十分ではないという点。構成、学習方法、適用場面、効果などを明らかにする記載が求められており、海外でもこのような論点が先行しています。
3. 日本における実務的な教訓
・日本国内ではまだAI特許を巡る大規模訴訟は少ないものの、将来的な紛争の火種となる可能性は十分にあります。
・たとえば、学習済みAIモデルの提供を受けて製品化した際に、元モデルのライセンス条件に反した場合の責任分担などが不明確なケースがあります。
・特許の明細書作成時における記載の抽象度や実装内容の明確性が、将来的な訴訟リスクに直結することも意識すべきです。
4. 訴訟予防のための対応策
・開発初期段階からの特許調査と回避設計の徹底
・共同研究や外部委託時の契約における知財条項の明文化
・ライセンス契約における使用範囲・再利用条件の明確化
・モデル更新や再学習による特許侵害リスクの継続的なレビュー
5. まとめ
AI技術の法的保護が重要視される中で、特許訴訟の動向を把握し、想定されるリスクに先手を打つ対応が必要です。単なる特許出願だけでなく、「争える特許」「守れる体制」の構築が、今後の知財戦略において不可欠となるでしょう。