◆はじめに
AI技術の急速な普及により、特許の保有だけでなく、そのライセンスを通じた活用も重要な戦略の一つとなっています。AI関連発明について他社とライセンス契約を締結することで、新たなビジネスモデルの創出や技術連携が可能となる一方、契約上の注意点も多く存在します。
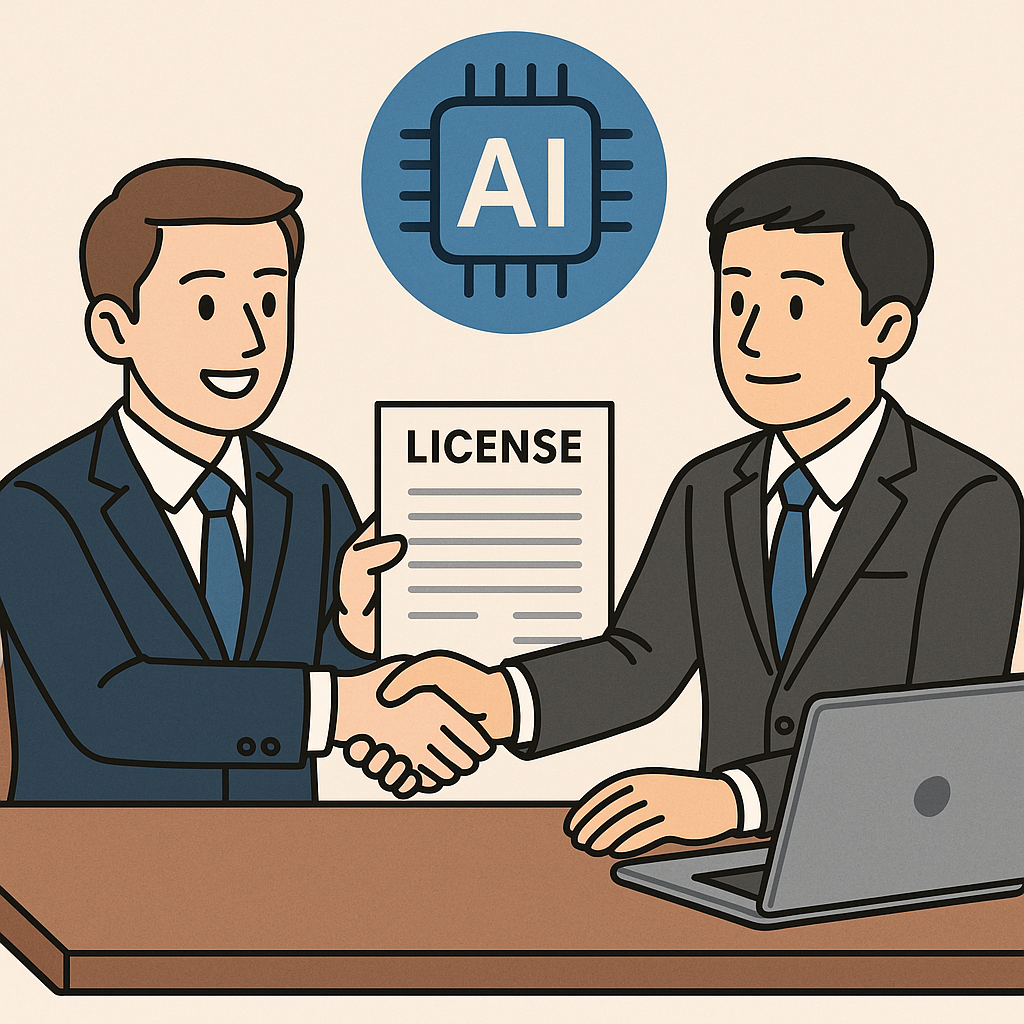
1. ライセンス活用の目的とパターン
AI関連特許のライセンス活用には以下のようなパターンがあります:
・自社特許を他社に使用させる(アウトライセンス)
・他社特許を使用する許諾を得る(インライセンス)
・クロスライセンス契約による相互使用
・共同開発における特許共有とライセンス
これらは、特許を「使う権利」として柔軟に活用し、競争優位を確保するための手段となります。
2. 活用例(国内外)
・国内企業A社が開発したAIモデルの推論手法について、米国企業B社に限定的ライセンスを供与し、B社のソリューションに組み込ませた例。
・欧州の研究機関が保有するAI画像解析技術の特許を、国内医療機器メーカーがインライセンスし、製品化を実現。
・複数企業間で共同開発されたAIフレームワークに関して、特許を共有しつつ、相互にクロスライセンス契約を締結。
3. 契約における主な注意点
AI関連特許のライセンス契約では、以下のような観点に注意が必要です:
・技術範囲の明確化:特許請求項と実施技術の整合性を確認する。
・ライセンスの対象:ソフトウェアコード、学習済みモデル、アルゴリズムのいずれに適用されるか明確にする。
・地域・期間・用途の限定:グローバルな使用を許諾するか、特定用途のみに限定するかを明示する。
・サブライセンスの可否:ライセンシーが第三者に再許諾できるかどうか。
・改良技術の扱い:ライセンス期間中に改良が加えられた場合の知的財産の帰属や共有の取り決め。
4. ライセンス交渉の実務ポイント
・契約前に特許の有効性や権利範囲についての技術的・法的評価を実施すること。
・必要に応じて、NDA(秘密保持契約)やMTA(素材移転契約)などの補助契約も併用する。
・自社の事業戦略に照らして、排他的ライセンス/非排他的ライセンスの選択を行う。
・税務や移転価格の観点からも、ロイヤルティの算定根拠を明確にする。
◆まとめ
AI関連特許は「保有する」だけでなく「活用する」ことで価値を生む知的財産です。特に、他社との連携やグローバル展開を見据えたライセンス契約においては、契約条項の細部にまで目を配る必要があります。自社技術の保護と活用の両立を図るため、専門家の助言を得ながら戦略的に取り組みましょう。