◆はじめに
AI技術は日進月歩で進化しており、その技術成果のすべてが必ずしも特許で保護できるとは限りません。特許制度には要件や限界が存在し、場合によっては他の知的財産制度や工夫を組み合わせて保護する必要があります。
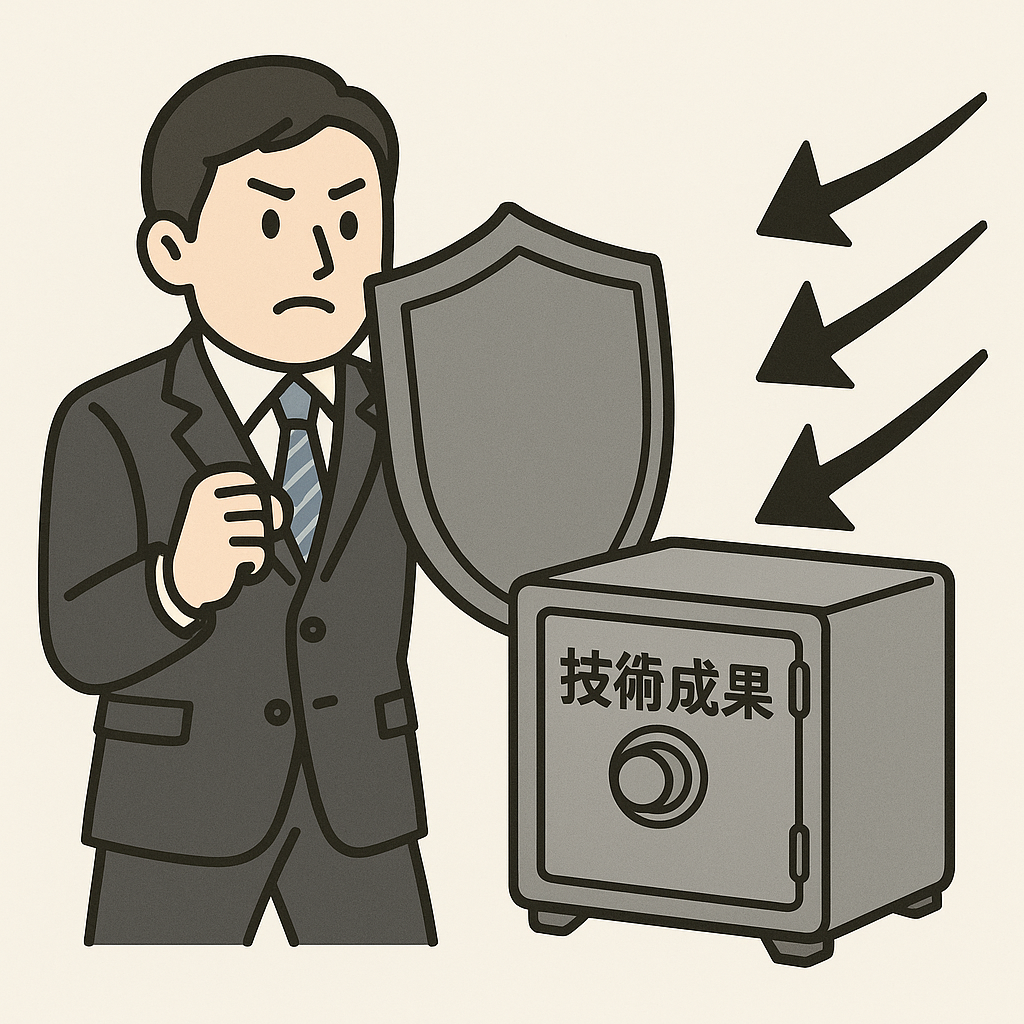
1. 特許制度の限界
特許として保護するためには、「技術的思想の創作」であること、「産業上の利用可能性」があること、「新規性・進歩性」があることなどの要件を満たす必要があります。しかし、以下のようなケースでは特許化が困難です:
・機械学習による出力結果そのもの(例:文章、画像、予測結果)
・単なるデータの収集・蓄積や、それ自体の構造
・技術的手段を欠く業務フローの抽象的な記載
・ブラックボックス的な記載で構成と効果の因果関係が不明なもの
2. 営業秘密による保護
特許化が難しいが、競争上重要な情報については、営業秘密として保護することが可能です。例えば、学習データセットの構成や収集方法、推論パラメータ、特徴量の選定基準などは、秘密として管理することで差別化要素を維持できます。ただし、「秘密管理」「有用性」「非公知性」という要件を満たす必要があります。
3. 著作権による補完
AIが生成するコンテンツ(文章、画像など)は、原則として著作物としての保護対象ではありませんが、その学習に用いたプログラムやUIデザインなど、人が創作した部分については著作権による保護が可能です。
4. 商標やブランド戦略
特許によって保護できないサービスやAIのネーミングについては、商標としての登録を検討することで模倣を防ぐことができます。AIが提供するサービス名称、UI上の名称などは、商標出願の有力な対象です。
5. データ契約や利用規約による保護
学習済みモデルや提供する推論APIなど、システム外部との接点がある場合には、契約や利用規約での制約が有効です。技術的保護と並行して、法律上の拘束力をもったルール設計を行うことで、知財としてのコントロール力を強化できます。
◆まとめ
AI技術の成果を保護するには、特許制度の枠内だけで考えるのではなく、営業秘密、著作権、商標、契約といった多様な手段を組み合わせて、全体として知財ポートフォリオを構築することが重要です。