◆はじめに
AI関連技術の開発においては、他社との共同開発や、外部からのAIモジュールの導入が一般化しています。しかし、これらの形態には特許出願や権利化の観点で多くの落とし穴が存在します。本稿では、そのようなケースで注意すべきポイントを解説します。
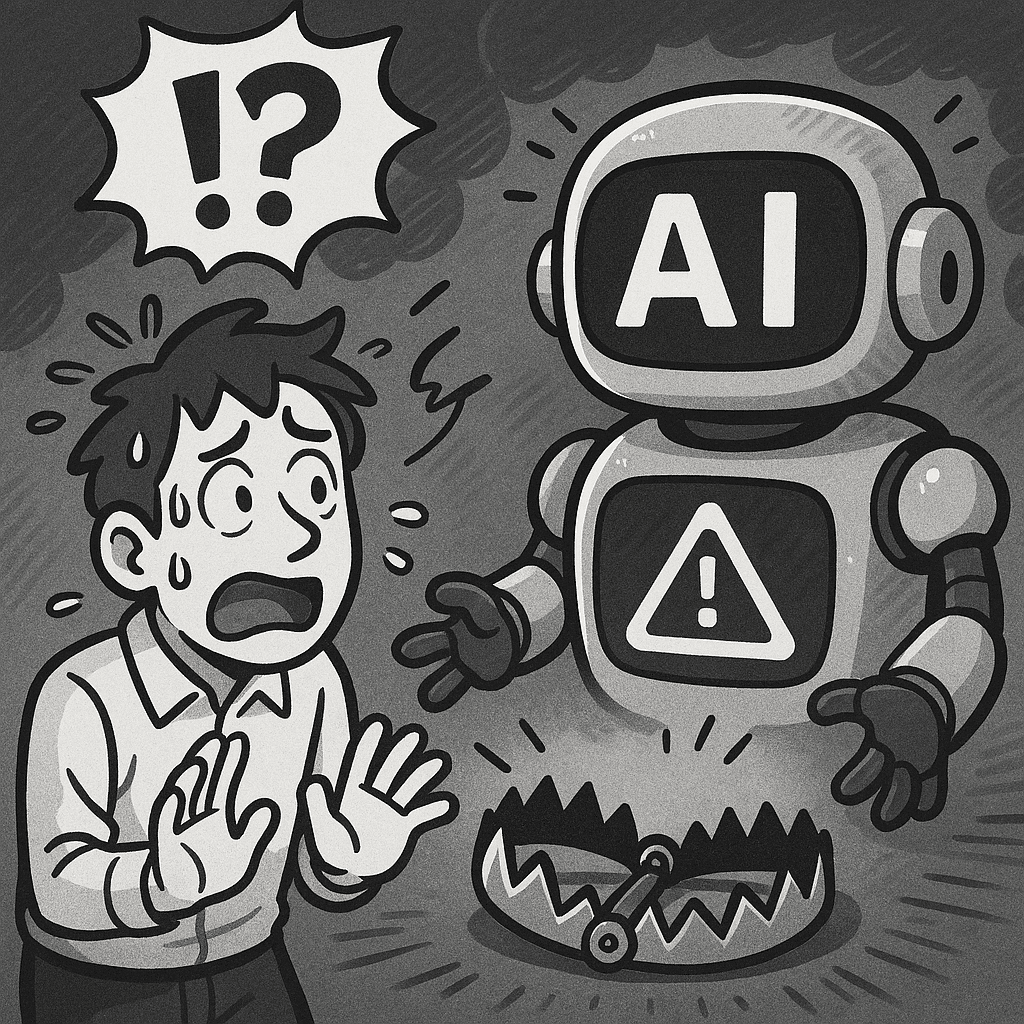
1. 共同開発における発明者の明確化
共同開発では、発明の内容ごとにどの企業の誰が“発明者”であるかを明確にすることが極めて重要です。単に参加したからといって発明者になるわけではなく、特許法上の“創作的貢献”があったかが問われます。この点が曖昧だと、出願人の帰属や発明者名の誤記につながり、無効理由にもなりかねません。
2. 出願人の取り決めと契約による調整
発明がどの法人に帰属するか、出願人として誰を記載するかは、共同開発契約による事前の取り決めが肝心です。契約が曖昧なまま出願を進めると、のちの特許移転やライセンス交渉でトラブルになるリスクがあります。とくに国際共同開発では、各国法制の違いも考慮しつつ契約書に明記すべきです。
3. 外注AIモジュールの利用とライセンス制限
近年、サードパーティのAIモジュールやAPIを活用するケースが増えていますが、これらの多くには再利用や二次配布、逆解析などを制限するライセンス条項が含まれています。特許出願時には、出願内容がこれらの契約に抵触しないか注意が必要です。また、外注モジュールが発明の中核を担っている場合、その貢献をどう扱うか(たとえば帰属や開示義務)は慎重な検討が求められます。
4. 学習済みモデルの著作権・権利帰属の整理
外注業者や他社が構築した学習済みモデルを利用する際、その学習データの出所や、モデルに対する著作権的保護・営業秘密性が問われる場合があります。これらの整理がなされていないと、特許に加えて秘密情報や著作権侵害のリスクも発生します。
◆まとめ
共同開発や外注モジュールの活用は、AI時代の開発には不可欠な戦略です。しかし特許戦略と両立させるためには、発明者の明確化、出願人の取り決め、外注契約の権利条項の把握など、事前に多角的な観点から整理しておくことが不可欠です。