◆「AI活用」はもはや特別ではない時代へ
近年、生成AIや機械学習などの技術が爆発的に普及し、「AIを活用した業務改善」や「AIを組み込んだサービス開発」は、大企業のみならず中小企業にとっても現実的な選択肢となりました。
しかし、「AIを活用したからといって、すぐに差別化できる時代」は終わりつつあります。同業他社も同様にAIを使い始め、すぐに模倣可能な機能やサービスでは競争優位は保てません。
では、どうすればAIを活用した技術やサービスを真に自社の資産にできるのか?
その答えのひとつが、「AI関連特許の取得」です。
弊所HPでは、「AI関連発明」について、AIの活用初期段階から特許出願、権利化後の活用までを、連載記事としてお伝えしていきます。
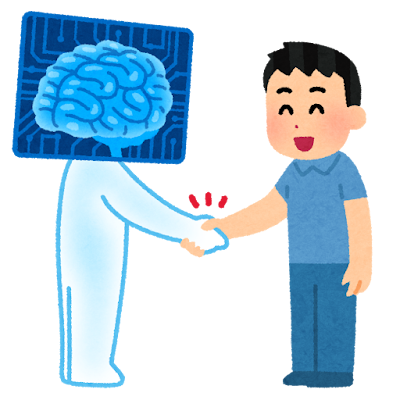
◆AI特許の注目度は年々上昇中
2024年の世界知的所有権機関(WIPO)のレポートによれば、AI関連の特許出願は前年比で大幅な伸びを示し、PCT出願のうち約20%(6万7,662件)がAI技術に関するものでした。さらに、米国では生成AIに関する特許出願が56%増の51,487件に達しています。この急激な出願増加は、AI技術が事業の差別化要素として急速に重要性を高めていることを示しています。
また、日本企業による出願件数も右肩上がりになっており、以下のような技術分野での出願が活発化しています:
– 医療診断AI
– 製造ラインの異常検知AI
– 小売・物流業務の需要予測AI
– 文書解析やナレッジ管理AI
特に、「自社業務に特化したAI利用の方法」は、ニッチであっても特許対象となる可能性が高く、他社に対する差別化を図る上で非常に重要です。
また、日本の特許庁HPでも、ビジネス関連発明の最近の動向についての情報を発信しています。
◆特許出願しないとどうなるか?
AIを活用した業務改善や新規サービスを開発しても、特許出願しなければ法的に模倣を止める手段がありません。逆に、特許出願をしなかった場合、以下のようなリスクが生じることが考えられます。
1.模倣リスク
同業他社に仕組みを真似され、競争優位が失われる
2.先願リスク
他社に似たアイデアで先に出願され、自社が実施できなくなる可能性
3.投資回収リスク
技術開発に投資しても、独占できずに市場価格が下がり、利益が出ない
このようなリスクを避けるためにも、「攻撃は最大の防御」と言うように、積極的な特許出願を検討していきたいところです。
◆「AIを使うだけ」では守れない時代に
多くの企業が「ChatGPTを業務に使ってみた」「画像生成AIで素材を作った」といった表層的なAI活用にとどまる中、特許取得は「技術的工夫を持ったAI活用」を行っている証拠となります。
例えば:
– 特定の業務フローに最適化された学習データの構築手法
– 出力精度を高める前処理・後処理の工夫
– 課題解決を目的としたAIの使い方の組み合わせやアルゴリズムの工夫
こうした要素は、きちんと構成すれば特許化が可能であり、実際に中小企業でも出願・取得に成功している例が増えています。

◆まとめ:AI時代の知財戦略は「先に守った者勝ち」
今後、AIの活用はさらに一般化し、「どのように活用しているか」「それをどう独占的に使えるか」が重要になります。技術的な工夫があるにもかかわらず、特許を出願していなければ、それはただのノウハウのままです。
逆に、知財の専門家と連携しながら戦略的に出願することで、自社のAI活用を「模倣されない資産」へと変えることが可能です。
AI関連発明について権利化をご検討されている方は、お気軽に弊所までお問い合わせください。